浄水器や排水処理装置の荏原製作所が機械や装置を売るのではなく、排水を綺麗にして流すシステムを提供する“モノからコトを請け負うサービス化”に転換しています。お客の悩みや不安を解決するために、工場内の設備や制御システムをIoTで結び集めたデータを使って生産効率を高める、モノづくりの生産ラインと管理システムを一括して売る「スマート工場」の販売が始まりました。
少量多品種の製品の生産を自動で調整できるよう、1つのラインにメーカーや工程が異なる機械が組み込まれていても、1台のパソコンで一括して管理できる方式で、切り替えにかかる時間が3分の1に短縮し、生産性を3割程度上げられるというシステムです。
工場の大小ではなくAI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)化で新しい 「スマート工場」とし、サービスの経済化が急速に進んでいます。我が社もお客さまの悩み解決に取り組んでまいります。

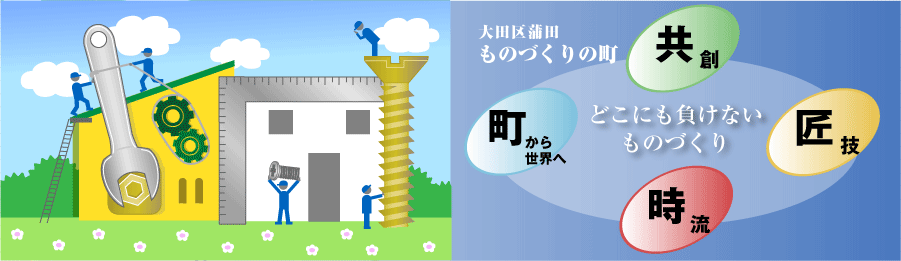
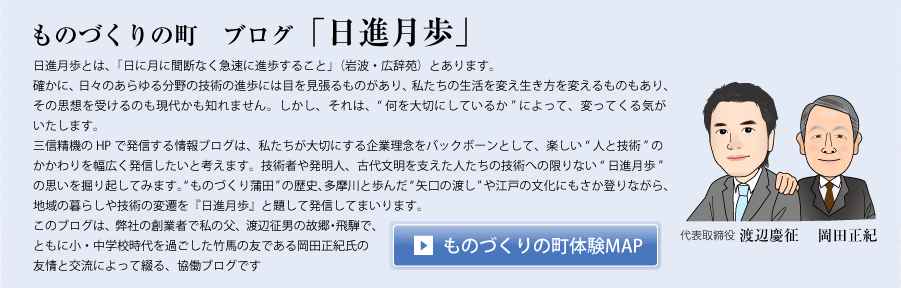
アーカイブ