歴史的に技術面で意義のある機械と科学技術の歴史や生活に大きな影響を与えた製品が、機械遺産と技術遺産として選ばれました。
今年10回目の機械遺産は、日本機械学会が「機械の日」に認定したのが富士重工業が1958年に販売した軽自動車スバル360、愛称「てんとう虫」など7件で、他に66年に商用地熱発電所として初めて運転を始めた岩手県の松川地熱発電所が選ばれています。
国立科学博物館が新たに登録したのは、ライオンが1999年に製造を始めた生活排水による環境汚染や洗浄効果と安全性を向上させた酵素パワーの合成洗剤「トップ」など16件が登録されました。
当社でも機械油に汚れた手を肌に優しく汚れを落とすとして開発された石鹸「クオリオ」がありますが、機械や技術の発展はいつも“必要の母”から生れるのですね。
Category Archives: 技術進歩について
広がるロボット君!
自動で動き回って床をきれいにするお掃除ロボ「ルンバ」が人気で、国内メーカーも「トルネオ ロボ」や、おしゃべりもできる「ココロボ」が売り出され玩具メーカーや家具、流通大手もPB商品で追いかけます。また、世界初という全自動洗濯物折りたたみロボ「ランドロイド」が登場し話題になっています。
今年の国際食品工業展では「食品ロボ」が人気になっています。ジャガイモの皮むき機はありますが芽を取る「芽取りロボ」やブロッコリーをカットするロボ、キャベツをサイズごとに分けるロボ、ご飯をほぐしながら好みの量を器に盛って、牛丼のタレをしみこみやすく盛る「シャリ弁ロボ」、アンズやプルーンの種取りをするロボなど個性的に進化しています。食品工場が注目するロボット達ですがファミレスや寿しやで人手不足を支援するための「働くロボット」が進化し始めています。人と機械の融合、私たちの精密機器の仕事は、家事代行へと広がっています。
飛騨市の地底から生れるノーベル賞
我が社の工場がある岐阜県飛騨市は、宇宙の謎を解明する施設が地底に集中し、世界が注目しています。ノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊さん、梶田隆章さんを輩出したスーパーカミオカンデが更に進化しています。
今年2月、アインシュタインの最後の宿題と言われる「重力波」を米国チームが初観測に成功したと発表し、早くもノーベル賞候補といわれていますが、本施設でも世界初の大型低温重力波望遠鏡「KAGRA(かぐら)」が完成し、7億光年のかなたから来る重力波による光のゆがみを観測する試運転が始まり、2017年度の観測開始に向けて取り組みがスタートしました。その他に、宇宙空間の4分の1を占める正体不明の「暗黒物質」の観測や、物質の原子核をつくる陽子が壊れる「陽子崩壊」現象の観測、ニュートリノを人工的に作って飛ばしたりと次のノーベル賞を目指した研究が進められています。宇宙の謎解きから新しい技術が生まれることは間違いありません。
第4次産業革命
米シリコンバレーで多くのITベンチャーが誕生し、科学技術の進歩は日進月歩で現代は「第4次産業革命」といわれています。
国も新成長戦略のテーマに第4次産業革命への対応を上げ施策の具体化を進めています。
ものづくり大国でありながら働き手が減少する日本と同じドイツでもその課題に対応して
・機械や製品を通信でつなぐ
・機械が自ら考えてものをつくる
・単純労働から働き手を開放する
を目標に第4次産業革命に着手しています。
国も世界最高水準の国立大学づくりを掲げ、大学発ベンチャーの創出を後押しする方針を決め、ITに強い人材育成を始めます。
職人の技を機械に伝承し「勘」の力をデジタルがつなぐ時代が始まっています。
高齢化、人口減少の社会で職人が失くなるのではなく職人と機械が新しく共存する産業革新であってほしいと願っています。
2030年の深海都市
宇宙に向うエレベーターもあれば、深海に向う海底 都市も現実に向って考えられています。
清水建設が2030年に完成を目指す深海都市構想で、その名も「オーシャンスパイラル」。
水深3千~4千 mの海底から海面にそそり立つ未来都市で、約5千人が暮らすまちです。
海面近くの深さ500mの所に建てられる球状の都市から下向きにらせん状の通路が延び、海底にあるメタン製造工場につながります。
海水の温度差で発電したり、海底の微生物で二酸化 炭素を燃料用のメタンガスに換えたり、途中には深海探査艇の補給基地を備えたりと新技術がいっぱいです。球の中心に立つ塔が住居やホ テルになりますが、深海都市は地震などの災害の影響を受けにくいメリットもあるそうです。コンクリートの代わりに樹脂を使い巨大な3Dプリンターで建設する計画で、総工費は3兆円、工期は5年と計画されています。町工場の技術も是非貢献したいものですが、未来技術の夢は無限ですね。
隣人になる“人工知能”
1956年にジョン・マッカーシー(計算機科学)の提唱から人工知能・AI(Artificial Intelligence)の研究が始まりました。SF映画に登場した人工知能は、1984年からスタートした「ターミネーター」や「マトリックス」などを思い出します。 1999年にソニーが家庭用犬型ロボットAIBOを発売し、感情を表現したり人との対話をする機能を持ちロボットを生活の中に取り込みましたが、 AIBOも“新たな科学技術分野の創造に寄与した”とされ、未来技術遺産に登録され過去の技術となっています。
人工知能の進化はめざましく、AIが将棋のプロ棋士を負かしたり、2021年度までに東大入試突破を目指したり、俳句や和歌を作ったり小説づくり までと研究が進んでいます。
AIは記憶や学習といった人間の知的活動をコンピュータに肩代わりさせることを目的とした研究や技術ですが、工場の自動化にも欠かせない分野であり生産人口減をカバーしたり、新しい価値創造に貢献することでしょう。
「バック・トゥ・ザ・フューチャー2」の世界を実現
1989年公開 の米SF映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー2」は、30年後の未来2015年10月21日にタイムスリップする物語です。
このSF映画に描かれた未来がどこまで実現したかを「タイム誌」が検証しています。
車型タイムマシン「デロリアン」は、ごみを燃料に走りましたがトヨタ自動車が次世代エコカーの燃料電池車(FCV)「ミライ」を売り出し、未来をアピールしました。映画で登場したテレビ電話や指紋認証システム、手を使わないゲームや目にかけて見る映像端末はウエアラブル端末で実現し、犬の散歩に利用された小型無人機はドローン、宙に浮く「ホバーボード」や足に自動的にフィットし動力を持つ靴も「足に自動フイット」するスニーカーとして 限定ながら作られ、登場した未来技術のほとんどが実現しています。SF物語が単なる夢物語ではなく、技術の目標であり進歩の支えだと思うと私たち技術家もたくさんの夢を語りあいたいと思っています。
「宙(そら)と地」の二人のノーベル賞
わが社の工場がある飛騨市のスーパーカミオカンデから小柴昌俊先生に続いて同じ
「ニュートリノの研究」で、ノーベル物理賞を梶田隆章先生が受賞され、師弟で
ノーベル賞受賞は初めての快挙です。前日には医学生理学賞を大村智先生が受賞され、
日本中に勇気と感動を2日続きで与えてもらいました。
以前このコラムで「ウロボロスの蛇」の話しましたが、梶田先生は素粒子で宇宙誕生の謎解きを
研究され、大村先生は地中の微生物から抗寄生虫薬イベルメクチンの開発をされ3億人以上の
人々を救った研究です。宇宙の起源も顕微鏡で見る自然界の微粒子の世界も同じだと説く古代
ギリシャ人の哲学を日本の二人の研究者が同時に受賞されたことに不思議な縁を感じます。
梶田先生の「私たちの研究は、すぐ何かに役に立つというものではありませんが、宇宙の
謎解きに若い人もぜひ参加してもらいたい」と言葉を寄せられました。私たちも
改めて基礎研究の大切さを感じています。おめでとうございます。
「宇宙エレベーター」への挑戦
戦後70年、さまざまな戦争史が語られていますが、史上最大の戦艦大和には世界で初めてのエレベーターがあったそうです。SF作家アーサー・C・クラークが構想したのは「宇宙エレベーター」です。そのSFの世界がカナダの企業によって、地上20kmの宇宙エレベーターの実現に向けて動き出しました。
世界で一番高いビルはドバイの「ブルジュ・ハリフア」で828.9mですからその20倍以上の高さで成層圏に十分至達する距離です。宇宙エレベーターのメリットは、この屋上に飛行場があり多段式ロケットを必要としないことで、給油や再飛行ができ燃料費を30%節約でき人工衛星の機能も肩代わりすることができることです。考案したカナダのThoth Technology社では、構造体を支える材料はダイヤモンド・ナノファラメントを提案していますが、強風を耐える能力が必要で揺れをどう支えるかが問題だとしています。費用は不明ですが、壮大な技術への挑戦ですね。
ロボットにも法律?
私たちの会社は精密機器のオーダーにも応える産業ロボット分野でも活動していますが、ロボットの社会的普及と変革・恩恵には素晴らしい発展があります。自動洗浄機に始まり、お掃除ロボ、介護ロボや災害ロボコンと進化し、いよいよ自動車も名前通り自動運動へと急速に進化しそうですが、人との共存に向けて法律の在り方が議論され「ロボット法学会」が設立されます。その理由は、自動運転の車が事故を起こしたら責任を取るのはメーカー?、乗っている人?。介護ロボが人にケガや骨折をさせたら誰の責任?。もしも、人工知能ロボが故障で危害を及ぼしたら――――と数々の法的問題が生じます。新たな法解釈や立法が必要で開発する私たちもあらかじめルールを作り、そのリスクが予測できれば開発にも力が入り責任も明確になります。
無人飛行体ドローンが急速に広がるなか、新しい秩序が必要なのと同じですね。

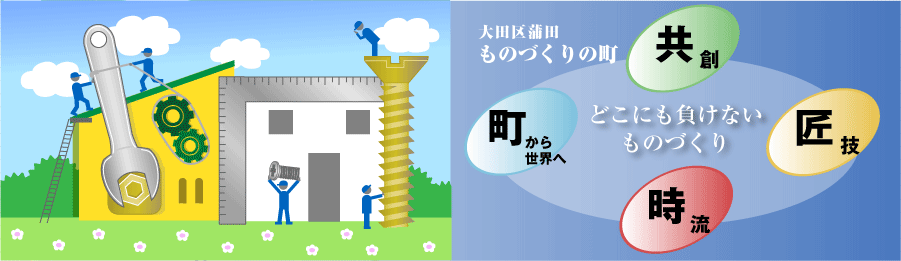
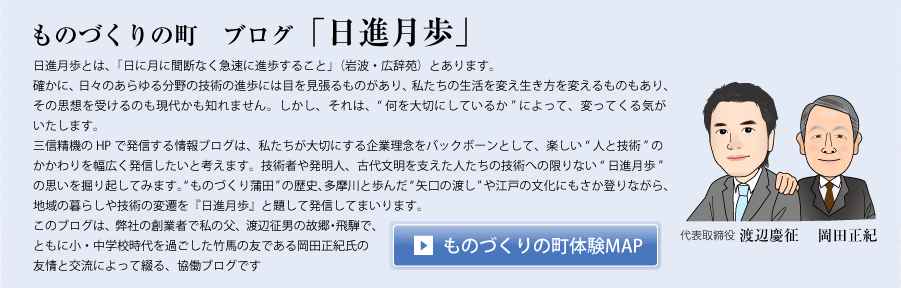
アーカイブ