“軟らかいロボット”-という新分野のソフトロボットが注目を集めています。
現在、活躍している均質な製品や部品の大量生産に対応し同じ作業をいち早くこなす硬いロボットアームに対し、卵をつかんだりトマトを収穫したりする人の手のような作業をするロボットの活躍が期待されています。
軟らかいモノを挟んでつかむ「バインド式アーム」や、人の動きを支援する「パワースーツ」、違和感が少なく装置できる「人工筋肉」と呼ばれるスーツも活躍しています。先端にカメラを取り付け、障害物に当たっても壊れず、対象を傷つけない「風船型アームロボ」が建物内の配管を撮影したり、医療現場での活用も期待されています。
「機械工学だけでなく、素材や電子制御、バイオの研究者が集まり“ソフトロボティクス”を発展させたい」と語られています。
当社も時代の要請と“ほどよい加減”のソフトロボ技術の発展に挑戦してまいります。

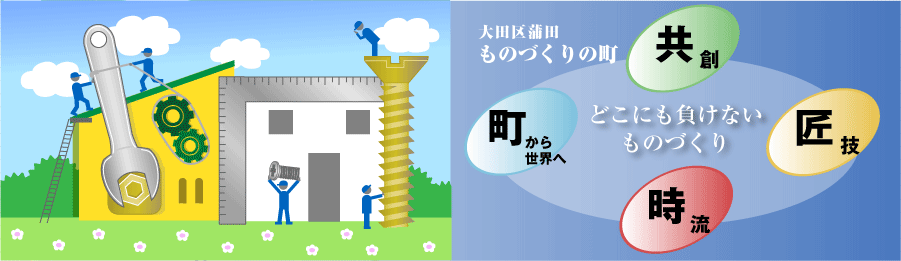
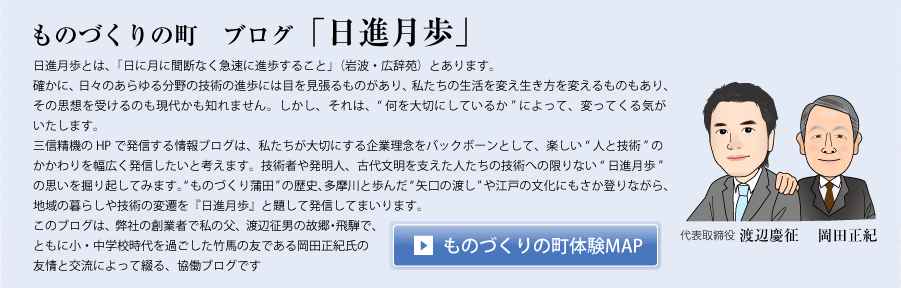
アーカイブ